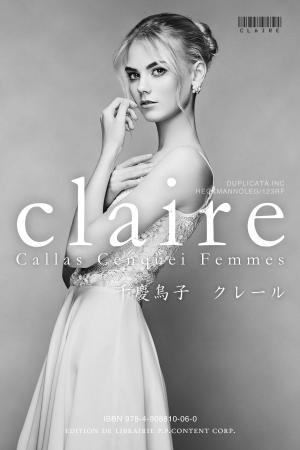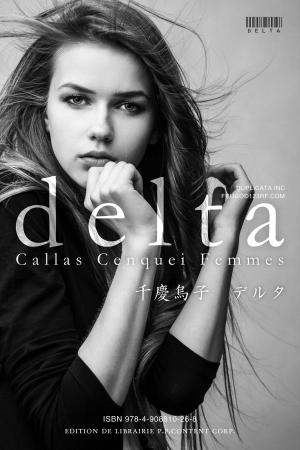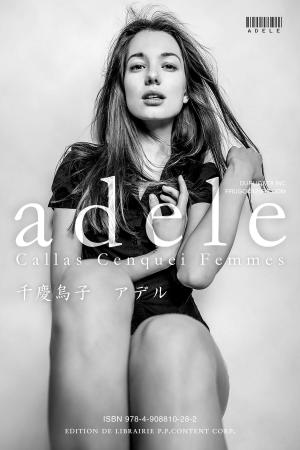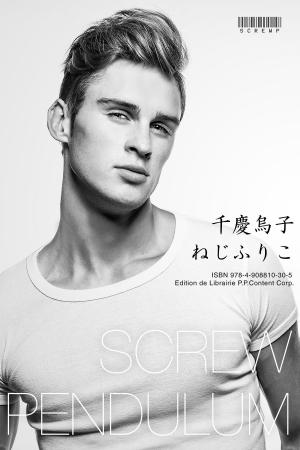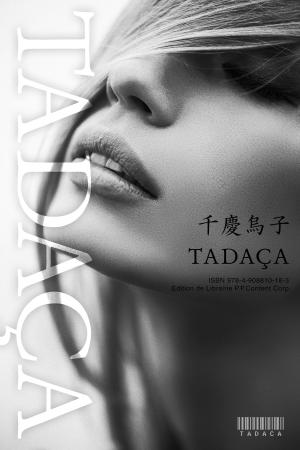P P Content Corp : 6 books
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: August 25, 2015
Language: Japanese
Release Date: August 25, 2015
自転車を押しながら坂道を登ってゆく彼女を見つけてマリと叫んだ。僕たちの夏の始まりだった。僕たちはその夏一緒に過ごそうと約束していた。誰にも内緒で、自転車を走らせ、一晩でいいから湖のほとりのコテージで一緒に過ごそうと二人だけの約束をしていたのだった。僕は彼女を見つけて名前を叫んだ。半袖のブラウスからのぞく肌という肌のすべてが美しく、額に結んだ粒のような汗までが美しかった。僕たちは夏の盛りの泡立つような虫の声に煽られながら…(本文より)
*...
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: October 7, 2006
Language: Japanese
Release Date: October 7, 2006
思えば、あの日はじめてサーカスの馬屋で見た中国男がわたしに微笑みかけることをせず、罌粟の咲き乱れる裏庭の片すみで、弦が一本しかない中国のセロを弾いてわたしたち家族を感嘆させることもなく、柔らかいなめし革のような肌を輝かせてわたしの手にうやうやしく接吻することもなく、そのまま馬に乗ってこの小さな村から出て行ってくれたのなら、どれほどよかったことだろうか──。
Claireとは明晰にして澄明、清澄にして純粋。光輝くような美貌の女クレールが繰り広げる愛の妄執はかくも清冽であり、またかくも甘美である。千慶烏子のプネウマティクとバロッキズモは、われわれの記憶の古層にたたまれた愛の神話を、かくも現代的な表象空間のもとでかくもモダンに上演する。アレゴリーとは他者性(アロス)の言説。千慶烏子が舞台の上に女たちを呼び寄せて語らせる甘美な愛の言説とは、実にこのアロスの言説、他者性の言説に他ならない。神の女性的な部分。狂気のもうひとつの側面。全体的で命令的な連続する快感。実に愛の妄執とは、ジャック・ラカンの言うとおり「女として現われる」のである。──急迫するファントーム。明晰な愛のオブセッション。目眩めくテクストの快楽、千慶烏子の長編詩篇『クレール』。
*...
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: November 15, 2005
Language: Japanese
Release Date: November 15, 2005
ヴィヨンよヴィヨン。おまえたちが太陽と呼ぶ、あの太陽の廃墟の太陽の、ファーレンハイト百分の一度の乱れがわたしの心臓を慄わせる。おまえたちが海洋と呼ぶ、あの海洋の廃墟の海洋の、高まって高まって高まって砕ける波の慄えがわたしの心臓をふるわせる──。
デルタとは誰か。それは謎めいたアナグラムなのか。それとも名前に先立つ欲望の集合的な属名なのか。きわめて今日的なカタストロフのもとでボードレールのファンタスムが、あるいはコルプス・ミスティクスのシミュラークルが、全く新しい光を受けて上演される。都市と売淫、断片と化した身体。あるいは石と化した夢。娼婦への愛は、果たしてヴァルター・ベンヤミンの言うとおり、商品への感情移入のハイライトなのか。ためらう者の祖国とは何か。...
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: July 23, 2003
Language: Japanese
Release Date: July 23, 2003
ヴィクトル・ユゴーの娘アデルの悲恋に取材した千慶烏子の長編詩篇『アデル』。その才能をして類稀と評される詩人の書き記す言葉は、あたかも暗室のなかの多感な物質のように、一瞬一瞬の光に触れて鮮明なイマージュを書物の頁に印しづけてゆく。そして恋の苦悩に取り憑かれた女を、その悲嘆に暮れるさまを、失意のなかで愛の真実について語ろうとするさまを、近接性の話法のもとで精緻に写しとどめる。傷ましいほどの明晰な感受性、あるいは極めて写真的なヴァルネラビリティ。
──そしてここ、ガンジーの浜辺でエニシダを挿した食卓の花瓶や静かに揺れるお父さまの椅子、その背もたれの縁に手を差し伸べて優しく微笑むお母さまの美しい横顔、もはや年老いて耳の遠くなったばあやがわたしを気づかって差し出してくれる洋梨のデセール、そのように取り止めもなく瞳に映るもののすべてが、海辺にせまる夕暮れの深い静寂のなかで、もはや決して繰り返されることはないであろう一刻一刻の美しい輝きをおびてわたしの眼の前に立ち現われたその瞬間、わたしは恋に落ちていることを確信しました。
*...
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: May 27, 1996
Language: Japanese
Release Date: May 27, 1996
Gender fluidity(流動的な性のあり方)――書くことの始まりにおいて、千慶烏子は、あたかも性の目覚めに遭遇した多感な少年が驚きをもって体験するように、あるひとつの「性の揺らぎ」に逢着する。それは必ずしも彼自身の性のあり方や性の自認に由来するものではない。むしろ、それは書くという行為そのものに内在している「性の流動性」なのだと言っていい。千慶烏子は、書くという行為のなかで、作者の性は揺らぎを帯びており、流動的であり、必ずしも彼自身が自認している性とは一致しないようなあり方でテクストの舞台に登場するという現象に遭遇して驚嘆する。普段よく知っている自分自身とは異なる何ものかがテクストの舞台に登場して「わたし」を語り、書く人を当惑させるのだ。
「あなたは妹の黒い靴下をはき、わたしはお兄さまの革のベルトをしめて、おたがいの胸乳をおのおのの口に吸い合うのです。あなたは妹の黒いリボンをつけ、わたしはお兄さまの黒い靴紐をしめて、おのおのの口に青い鱒をつりあげるのです。水しぶきをあげて勃起している青い魚をおたがいの口にさがしあてては、それをおのおのの口に吸い合うのです。そうしてあなたはわたしの野良猫のようにまるいおなかに、そうしてわたしはお兄さまの牝猫のようにきれいなおしりに、杜撰な虚言を突き立てあってはおたがいの青い鱒をおのおのの口に吸い合うのです。」(千慶烏子『やや...
by 千慶烏子
Language: Japanese
Release Date: October 14, 2001
Language: Japanese
Release Date: October 14, 2001
人類の歴史にはじめてインターネットが登場したときに、人はどのような未来をそこに見いだし、詩人はどのような書物をそこに創造したのか──。
本書はSWFフラッシュ形式のデジタル作品として2001年に初版が出版された。わが国で最初かどうかは断定できないが、デジタルで書物を出版するという企ての最も初期に位置するものであることだけは間違いない。以来2003年、2007年、2011年と本書は版を重ねている。これはよく売れるから版を重ねているのではなく、伝統的な出版文化に慣れ親しんだ文学者が、デジタルと遭遇したときに、これをどう受け止め、そして作品の中でいかにデジタルを内面化し、またいかにしてそれをデジタルで表現するかに費やされた文学的営為の記録である。今回の電子書籍版を含めると、千慶烏子は、都合五回におよぶ出版と二十年の歳月を本書に費やしている。
先駆者の営為はそういうものなのかもしれないが、必ずしも正当に評価され、必ずしも正当に次代に受け継がれるものであるとは限らない。むしろそれは忘れられ、忘却の淵に沈み、長い年月を費やした後にあらためて発掘されるものであるのかもしれない。本書『TADACA』も発掘の時を待って忘却の淵に沈んでいると言っていい。千慶烏子が完成に十数年費やした本書オリジナル版は、映像と音響とテクストの融合したマルチメディア的なデジタル作品として制作された。その先進性と高度な芸術的達成に対し、当時は国内よりもむしろ海外から熱い賞賛が贈られたものであると聞く。制作に十数年を費やしたというだけあって作品の完成度は高く、映画『ラ・ジュテ』を思わせるモノクロームの映像と海辺の環境音が交差する本書オリジナル版は、まさしく「読む映画」と呼ぶにふさわしい段階に達している。おそらく詩人は、この映像・音響・言葉の重層する空間にデジタル化された書物の来るべき未来を見たのではないだろうか。
しかし、デジタル黎明期の詩人が見た夢は、テクノロジーの進化によって、容易く覆されることになる。携帯型デバイスの登場とその爆発的な普及により、千慶が情熱を傾けたSWF形式のフラッシュは廃れ、エディトリアル・デザインもまた、美的に洗練されたソリッドなレイアウトからマルチデバイス対応のリフロー型のデザインが主流になる。書物をめぐる洗練された美的な企て、あるいは芸術家の野心的な企ては、電子出版にとって無用の長物となる。2010年になると、電子書籍の国際的な標準規格が策定され、規格の統一が進む一方、書籍コードのデジタル適用のガイドラインが提案され、誰でも本を出版することができるという謳い文句のもとで、デジタル出版は画一的になり、平準化する。実験的で先鋭的な性格は失われ、大衆的で商業的な性格が強くなる。しかし、これはテクノロジーが普及し、広範な支持を獲得してゆく中で辿らざるを得ない一連の過程であるにちがいない。おそらく今日の読者の皆さんからするならば、千慶烏子のデジタル出版は、都市と都市とを結ぶ航空路が発達するはるか昔、大空に限りない夢とロマンを見たライト兄弟の絶えざる不可能への挑戦を思い浮かべていただくといいのではないだろうか。
この絶えざる不可能への挑戦のなかで、千慶烏子は、デジタルの登場という歴史的現象を哲学的な問いかけとして受け止め、これを内面化してゆくことになる。本書は、しばしば難解と言われる千慶の書物の中でも特に難解な作品である。この解説では、しばしその難解さに分け入って本書を簡単に概観してみたい。
本書『TADACA』は四章からなり、それぞれテクスト論・書物論・写真論・欲望論の「批評」を横糸に、二人の男女の不可能な愛の行程を描く「詩編」を縦糸に、作品は織り成されている。読者は交互に配された批評と詩編を読むことで、縦横に織り上げられたテクストの襞、文彩、織り込まれた模様を読み解いてゆくことになる。平易な作品を読み慣れた読者には、この構成は難しく映るかもしれない。だが、難解さに直面して辟易するよりも、詩編と批評の間を、テクストの織り目を、織り上げられたテクストの襞を辿りながら、デジタル黎明期の詩人が見た光景にひと時たゆたってみるのはいかがだろうか。それはわれわれの今日に直結する過去であり、過去の中に眠っている未来であり、未来において発現するであろう過去であり、これを紐解いてみることはわれわれの今日をより有意義なものにしてくれるにちがいない。
特に第三章「La...